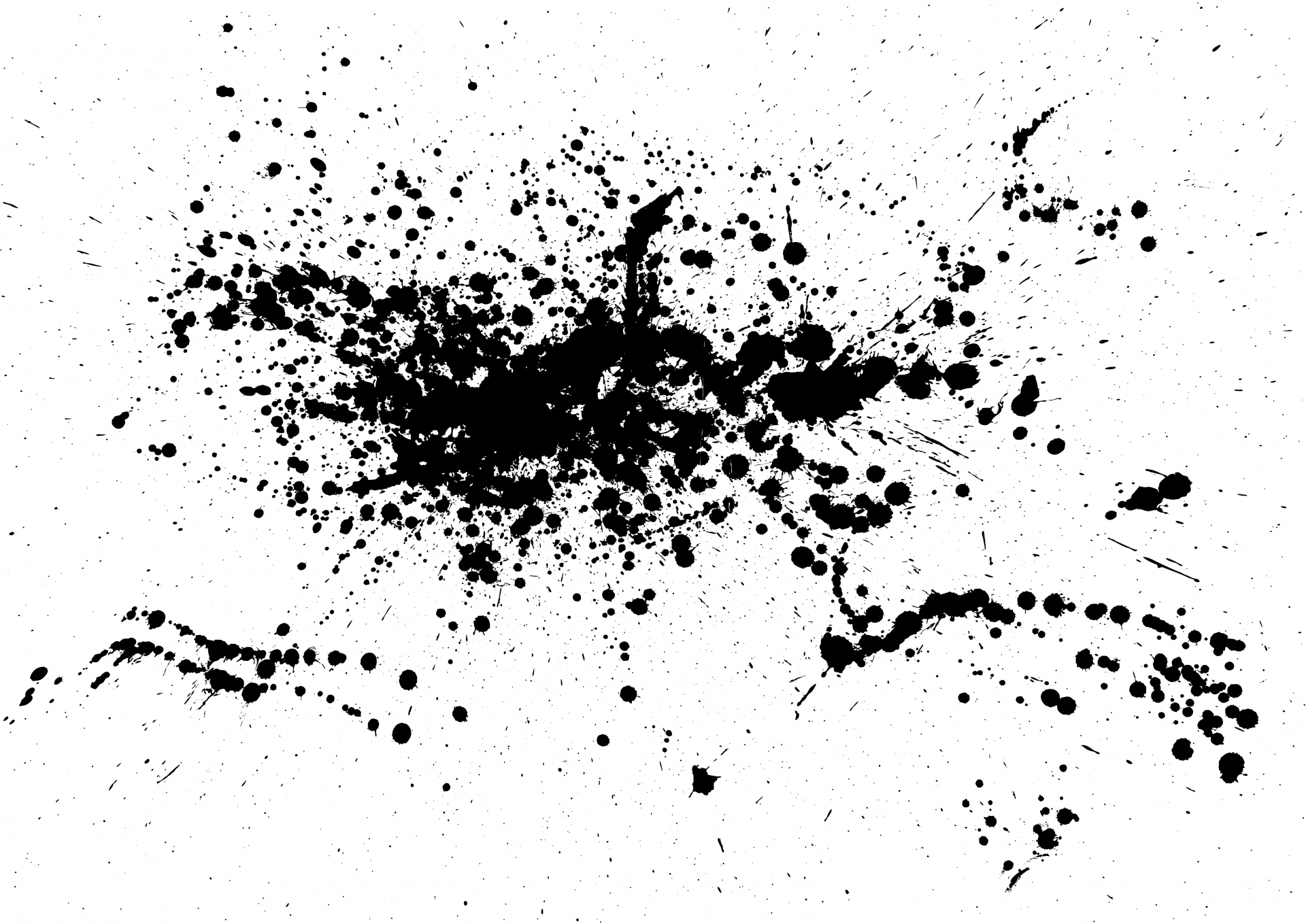お芝居や音楽鑑賞に行く時、「上手」と「下手」という言葉を耳にすることがあります。この言葉の由来は一体何なのか、気になった経験がある人もいるのではないでしょうか。
ここでは、上手と下手の由来についてお伝えします。由来を知ると、古くからの歴史を垣間見ることができますよ。
また、観客席から見たときの上手と下手の覚え方や、バンドや司会・漫才・落語などの、色々なシーンでの上手と下手についてもご紹介します。こちらも是非参考にしてみてください。
スポンサーリンク
関連のおすすめ記事
-

ゴキブリ対策はハーブを植えると効果的!おすすめハーブと活用法
家の中に発生すると嫌な害虫の代表格がゴキブリです。ゴキブリを発生させないために、色々なゴキブリ対策を...
-

マンションのキッチンが狭い!収納や作業スペースを確保するコツ
お住まいのマンションのキッチンが狭く、収納や作業スペースの確保に困っている人もいるのではないでしょう...
-

朝の支度を早くするための時短テク!今より早く準備ができる方法
朝の支度はいつもどのくらいの時間がかかっていますか?忙しい朝の準備は、1分でも早くしたいもの。少しで...
-

アパートにおすすめ。素敵なインテリアキッチンのアイディア色々
賃貸のアパートのキッチンは飾りようがないと諦めないでください。アパートのキッチンはスペースがない...
-

ゴキブリ対策にアロマが有効!レモン成分のアロマの効果について
お家にゴキブリが発生したら、と考えただけでも嫌な気分がします。他の虫でも家の中に入り込むのは嫌なのに...
スポンサーリンク
上手と下手の由来は?中国を参考にした上手と下手の由来
上手、下手の由来は元々中国から来ています。
中国には黄河と揚子江という中国を代表する2つの大きな川が、西から東に向かって流れているという理由で西が上、東が下という考えが生まれたことが関係します。
中国の皇帝は、「北極星を背に座るもの」であったため、南向きという決まりがあり、南の方から見た時、西は左で東は右に来ます。
ここから、左が上手で右が下手という風習が生まれたのです。
そして日本は都を作るときに中国を参考にしたので、天皇が南を向くという習わしがそのまま引き継がれ、左手に来る東側からは日が昇るため、理由は違うものの左が上手で右が下手という習わしが定着しました。
上手と下手の由来・日本では天皇から見た位置で上手と下手が決められていた
上手と下手は、天皇から見た目線で決まってました。
そのため、天皇から見て左側が上手、右側が下手です。
ちなみに天皇の次に高い位なのが左大臣と右大臣で、この二人の中では左大臣の方が位が高いです。そのため、左大臣は上手である左にいるものなのですが、これはあくまで「天皇から見て左」です。
そのため、大臣や使用人側から見ると、左大臣は右側にいるのです。
これは後ろにいる天皇から見た向きで配置されているため、私達から見たら逆向きに座っているように見えるのです。
由来を知ったら次は上手と下手を観客席から見たときの覚え方
舞台でも観客から見たら右が上手で左が下手です。
大体指揮者や司会者は下手から登場するものなので、人の出入りがある方が下手と覚える人もいるのですが、奏者は上手からも入場します。そうなるとこの覚え方ではどちらが紙てか覚えられません。
こういうときは、必ずと言ってもいい程ほぼ間違いなく下手にくるとても分かりやすい楽器があるのでそれで覚えたほうが覚えやすいのでコツをお教えします。
その楽器とは、ピアノです。
パーカッションと呼ばれる打楽器奏者も下手で演奏することが多いのですが、時々ステージ上段で演奏している場合もあります。
ところがピアノは、ソロがある場合以外は場所が変わることがほとんどありません。ステージ裏でも下手の袖にピアノが収納されているので、ピアノは下手と相場が決まっていると言ってもいいほどです。
色々なシーンでの上手・下手「バンド」「司会」の上手と下手
舞台と名のつくものは基本的にほとんど上手と下手があります。
バンドもそうです。バンドはステージを丸く使うので分かりにくいかもしれませんが、やじはり観客から見て右側は上手に変わりません。
舞台でよく見かける司会者の立ち位置も下手と決まっています。
舞台裏ではマイクスタンドも下手側に置かれており、そういった道具の出し入れも必ず下手側から行われます。
「落語」や「漫才」にも上手と下手がある
落語も漫才も舞台上で行うものなので、当然上手と下手があります。
玄関を開ける演技も、下手側から開けているように演じるのです。
伝統のあるものだからこそ、師匠から何代もの弟子にまででしっかり徹底されて教育されているというのが素晴らしいですね。
また、漫才にも上手と下手があります。真ん中から登場するステージもありますが、媚態は基本的に下手から登場する決まりです。
ではボケとツッコミに上手と下手があるのかというと決してそういう訳ではなく、ツッコミの人がどちらの手だと突っ込みやすいかで決めているコンビが多いようです。
多くの人が右利きなので、ツッコミの人も右手の方が突っ込みやすいという理由から、客席から見て右手にツッコミの人が立つというケースが多いようですが、名牡蠣な決まりはありません。
ステージや舞台を見ることがあったら少しそこに注目してみるのも面白いですよ。